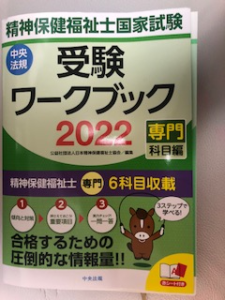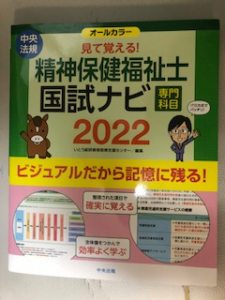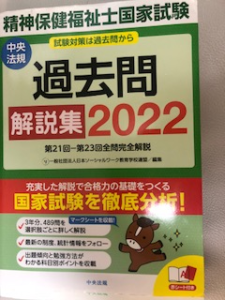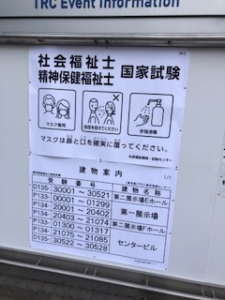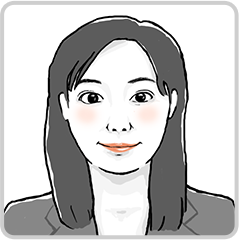――弁護士を目指したきっかけや理由について教えてください。
最初のきっかけは、小学生の頃に、知的障がい者の方の刑事裁判について書かれた本を読んだことです。著者の副島洋明弁護士は、知的障がい者の方の刑事裁判の弁護を多く担当していて、知的障がい者の方の人権擁護のために活動していました。副島先生の活動について書かれた本を読んで、子どもながらにとても感銘を受けたことを覚えています。
大学に入学した当初は、羽を伸ばそうと思っていたのですが、司法試験を目指す志が高い周りの人たちに影響を受けて、忙しい毎日でした。司法試験予備校で勉強する一方、家庭教師や塾講師、法律事務所でのアルバイトもかけ持ちしていました。
――注力分野とその分野に注力している理由について教えてください。
特に、福祉・保育・相続分野に力を入れています。これらの分野に詳しい専門家とも協力しながら、1つ1つの案件に取り組んでいます。
法律的な部分は弁護士が解決できますが、それだけでは十分な支援ができません。法律の知識ではカバーできない問題の解決や心のケアが必要な場合は専門の相談員につなぎ、依頼者を総合的にサポートしています。
借金の問題を例として挙げてみますと、自己破産などの手続きは弁護士が対応しますが、借金の背景にアルコール依存などの心の問題がある場合は、専門の相談員につなぎます。また、離婚問題を抱えている方やDV被害者は、精神的にダメージを受けている状態なので、メンタル面をケアするために専門の相談員にサポートを依頼します。
私自身も、弁護士になってから日本社会事業大学に通い、社会福祉士の資格を取りました。社会福祉士は、福祉や医療保険サービスと連携して、障害などによって日常生活を営む上で支障がある人を支援する仕事です。この資格を取得したことで、福祉や保育の専門家とのネットワークが広がり、より手厚いサポートを提供できるようになりました。
――弁護士として活動してきた中で印象的だったエピソードを教えてください。
知的障がいのあるDV被害者の方が、一時的に避難するにあたり、環境が悪い宿泊所に滞在することになってしまい、私に電話で助けを求めてきたことがありました。
私が迎えに行ったところ、土下座するほど感謝されたのですが、「土下座して謝らないと、自分の権利を守れない人生を送ってきたのかもしれない」とやりきれない思いを感じました。こうした方たちが、土下座なんてしなくても気兼ねなく生活できる世界になればいいのに、と思ったことを覚えています。
また、アパートで一人暮らしをしていた高齢者の方が認知症になって、ドアに鍵をかけて閉じこもってしまったことがありました。私と警察とヘルパーさんとで一緒にアパートに行ってドアを開けたら、その高齢者が頭から血を流して立ち尽くしていたんです。
私と警察がどうしていいかわからなくて戸惑っていると、ヘルパーさんが躊躇なく部屋に入って、ケガの状態を確認しました。その姿を見て、介護に携わっている人たちの凄さを感じました。
福祉分野の仕事をしていて感じるのは、介護や保育は大変な仕事の割に給与が安かったり、クレームを受けたりしやすいことです。介護や保育の事業所で顧問弁護士がついているところは多くありません。このような業界で働いている人たちを法的に保護するために、予防法務にも取り組んでいきたいです。
――仕事をするときに心がけていることは何ですか?
依頼者が安心できるよう、できるだけ迅速なレスポンスや丁寧な説明を心がけています。また、私が「こうするべき」と意見を押し付けるのではなく、依頼者自身がどうしたいかを大切にしています。
――自身の強みは何ですか?
福祉分野のネットワークを持っていることです。私1人では対応が難しいと思ったら、信頼できる社会福祉士と協働したり、支援団体につなぐなど、他の弁護士よりも問題解決のための情報や手段を持っていることが強みです。
――社会に対してどのような問題意識を持っていますか。
女性やLGBTQの方が、辛さや理不尽を感じていても、なかなか声を上げられない状況にあることです。女性にとって、働く環境が整っていないとも感じています。また、待機児童が依然として多く、放課後に児童が過ごす場所が不足していることも問題視しています。
私は、埼玉県の男女共同参画審議会にも委員として参加しているので、これらの問題について、他の専門家たちと一緒に社会に提言していきたいです。
また、日本は少子高齢化社会ですが、埼玉県は今後、特に急速に高齢化が進む地域です。
無縁社会と言われていますが、独身の方、ご夫婦で暮らしていてお子さんがいない方、お子さんがいてもお子さんが遠方であったり、お子さんに障がいがあったり等、身内に頼れない方は今後増えていくと思います。このような方たちには、成年後見制度や任意後見制度の活用、遺言書の作成などにより、その方らしい人生を送ることができるようにサポートができればと思っております。
SOSを出し続けてほしい
――休日はどのように過ごしていますか?
料理が好きなので、煮込み料理やお菓子を作っています。あとは、ブログを更新したり、法律を一般の方にわかりやすく伝えるための漫画の構想を練ったりしています。
――趣味は何ですか?
漫画を読むことです。
子ども達と接するときに、最近の漫画を知らないと話が合わないので、『鬼滅の刃』、『呪術廻戦』、『スパイファミリー』など話題作はもちろん読んでいます。児童養護施設に漫画を寄付する活動もしています。
漫画を読むことで、世の中にはいろいろな人がいることを学べますし、心が豊かになります。子ども達が健康で文化的な生活を送るために、漫画は重要な役割を果たしていると思います。
個人的に好きなのは、荒川弘先生の『鋼の錬金術師』や、歴史や心理を扱った女性漫画家の作品です。特に、池田理代子先生の『ベルサイユのばら』、山岸凉子先生の『日出処の天子』、萩尾望都先生の『イグアナの娘』がお気に入りです。家族を描いた宇仁田ゆみ先生の『うさぎドロップ』、よしながふみ先生の作品も好きです。
あと、保育士なので、子どものおもちゃを見たり、絵本や児童文学を読むのも好きです。 特にお気に入りは、ミヒャエル・エンデの「モモ」や「はてしない物語」です。
――今後の展望を教えてください。
漫画、紙芝居や講演などを通して、法律をわかりやすく伝える活動をしたいです。法律は、よりよく暮らすために誰もが知っていた方が良いツールだと思うからです。実際、これまでに成年後見紙芝居を作成し、上演していただいたこともあります。
また、介護や保育の事故に関する予防法務や、親族に頼れない方の遺言書の作成や任意後見制度を使ったサポート、児童養護施設や乳児院などの施設と弁護士などの専門家をつなげる仕事ができたらいいなと思います。
――法律トラブルを抱えて悩んでいる方にメッセージをお願いします。
難しいかもしれないけれど、まずは誰かにSOSを出すことがとても大切です。SOSを出してもすぐには気付いてもらえないことや、自分に合う相談相手が見つかるまでに時間がかかることがあるかもしれませんが、諦めずにSOSを出し続けてほしいです。
皆さんにとって弁護士はまだ遠い存在かもしれませんが、少しでも身近な存在に感じてもらい、頼っていただけるように、私たちも努力していきたいと思います。