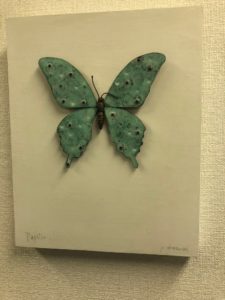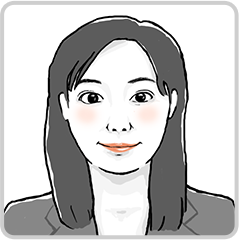こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
今日は、今話題の漫画「凪のお暇」を題材に、親子間のモラル・ハラスメントに関してお話をしたいと思います。
凪のお暇は、いろいろな要素が詰まった漫画のため、ある人には節約術の漫画、ある人にとっては恋愛の漫画・・・と、見る人によって景色が変わる漫画だと思います。
私は、凪のお暇を「母子(親子)間のモラル・ハラスメントの漫画」として捉えています。
主人公の凪は、とても空気を読む、周りからすると非常に謙虚で良い子(都合の良いという側面も)ですが、自己評価の低さによる生きづらさを抱えています。
——-(ここからは漫画のネタバレもありますので、それを踏まえてお読みください。)——-
凪のお母さんは、表面的には凪に優しいように見えるし、殴る蹴る・暴言を吐くなどの目に見えた虐待行為はありません。
しかし、凪のお母さんは、凪のことを一人の人格として認めていません。
凪のお母さんは、凪を器のように捉えており、凪に自分が思ったように、自分が望んだように発言をしたり、暗に行動するように仕向けてきます。
例えば、凪たちの親戚の子の結婚式を「大したことはない」と悪口を言うように暗に仕向けておきながら、それを凪の意思で悪口をいったように装うのです。
親子というのは、対等な関係ではありません。
特に子どもが小さい頃は、母親に愛されないと子どもは生死にかかわるので、一生懸命に母親に好かれるようとするのです。
凪のお母さんは、凪のその感情を利用して(自覚があるか分かりませんが)、凪が言いたくもない悪口を、自分を喜ばせるために、さも凪の本心であるかのように言わせるのです。
なんだかわかりにくいですが、このわかりづらさ・表面的には見えづらい悪意がモラハラの本質です。
この漫画の中では、親子間のモラル・ハラスメントの様子がすごくさり気なく書かれているので、お母さんとの関係で何か違和感を持っている方は、ぜひ読んで頂きたいです。
凪も、お母さんに自分の人格を認めてもらえず、自分が望むことではなく、お母さんの空気を読んで、お母さんの機嫌を取ることに徹してきてので、自己評価が非常に低い反面、空気を読むことに長けた人格になっており、生きづらさを抱えている反面、仕事では評価される面もあります。
しかしながら、「凪のお暇」の素晴らしいところは、そのような生きづらさを抱えながらも、凪が成長し、少しずつ自己評価を変えていき、自己主張ができるようになってくるなど、お母さんに作られた檻から脱しようとしている過程が描かれています。
親子間のモラル・ハラスメントはわかりづらいので、わかる人にはわかるし、わからない人にはわからないというのが現状です。
そのような中で、「凪のお暇」がヒットしているのは非常に望ましいことですし、毒親に苦しんでいる子ども側に勇気を与えるものだと思います。
両親に感謝すべきことは原則論ですが、あくまで例外があります。
「凪のお暇」は、単純な恋愛漫画ではなく、親子関係など、多様な側面が描かれている点で、素晴らしい漫画です。
皆様もよろしければ、主人公の凪とお母さんの関係にも注目して下さいね。