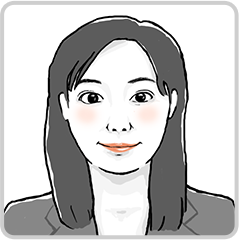こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。
本日(令和4年2月20日(日))、埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉主催の『第36回 支援者のための成年後見活用講座』の講師を務めました。
主に、法定後見制度と任意後見制度の概略について解説をしました。
講座参加者の方の中には、地域包括支援センター職員の方も多く、法定後見制度と任意後見制度に、高い関心を示されていました。
以下、簡単に説明をしたいと思います。
成年後見制度には、以下の2種類があります。
・法定後見制度(成年後見・保佐・補助の3つ)
・任意後見制度
【任意後見制度とは】
本人が任意後見受任者との間で、あらかじめ公正証書によって締結した任意後見契約に従って、本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者が任意後見人となり、本人を援助する制度
である。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに任意後見契約の効力が生じる。(任意後見法4条1項、2条)
では、任意後見制度はどんな人が利用しているのでしょうか?
【具体例1】
知的障がいのあるお子さんA君のご両親が、自分たちが亡くなったときにA君をお願いする人を探している。
お願いをする人は誰でも良いわけではない。この人に、というこだわりがある。
→任意後見制度にしよう。
【具体例2】
私は生涯未婚で、子どももいない。両親も既に亡くなっている。
兄弟や甥っ子は、私にお金の無心ばかりするので、将来頼りたくない。私が認知症になった場合に、誰も成年後見人の申立てをしてくれないかもしれない。あらかじめ頼む人を決めておこう。
→任意後見制度にしよう。
【法定後見制度のメリット】
1.費用が安い。(通常、成年後見人1人分の報酬で済む)
2.悪用される可能性が低い。(最初から裁判所の監督があるため)
【法定後見制度のデメリット】
1.親族がいない場合に、上手く市長申立てをしてもらえないと、いつまでも必要な人が成年後見人制度を利用できない場合がある。
2.好きな人を成年後見人に選べない。本人親族からして当たり外れがある。
【任意後見制度のメリット】
1.好きな人を任意後見人に選べる。
2.任意後見契約は自由度が高いので、事前にお願いしたいことについて、細かいオーダーをすることができる。
【任意後見制度のデメリット】
1.最終的に、任意後見人と任意後見監督人の2つの費用がかかるので、費用が高くなりがちである。
⇒この対策として、任意後見人は本人の親族が無償でなり、任意後見監督人にだけ報酬を払うという方法もあります。
2.公証役場で任意後見契約を締結するにもお金がかかる。
3.好きな人を選べる反面、親族間の対立紛争に利用される。